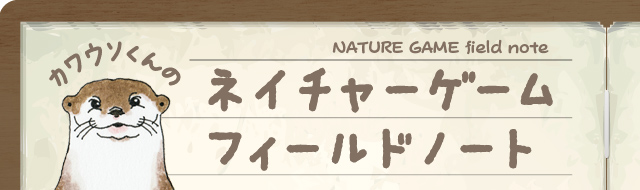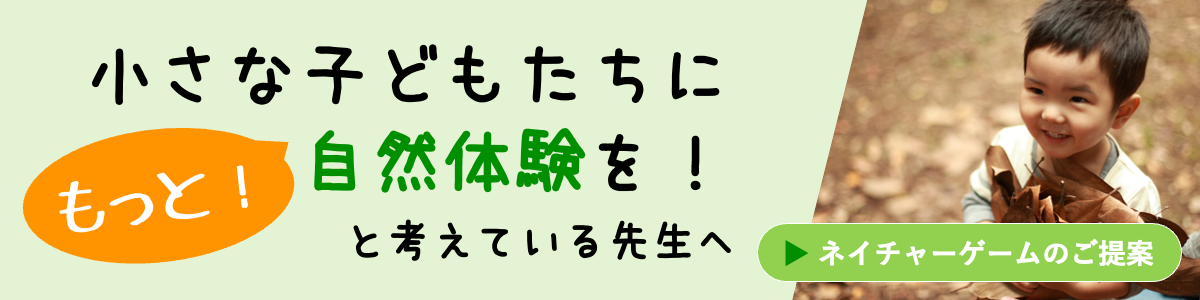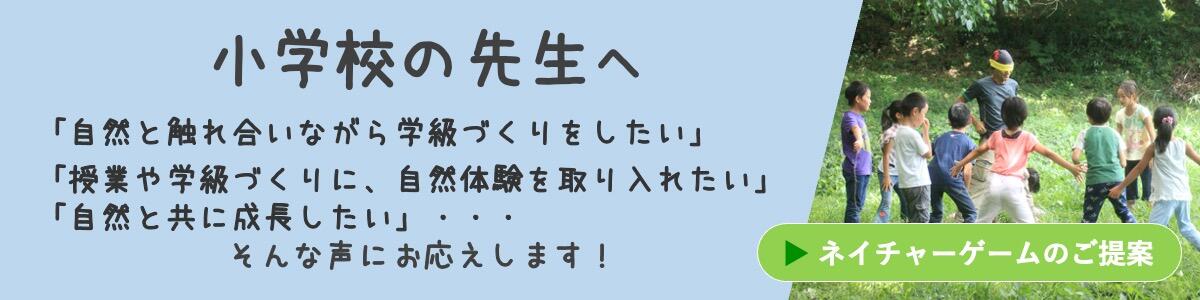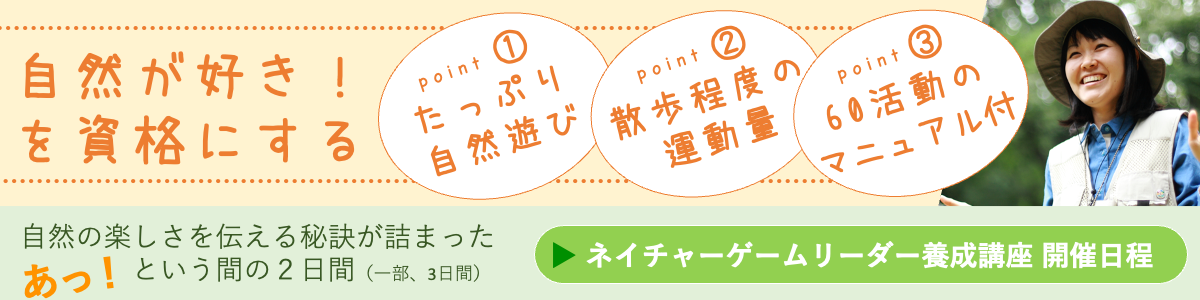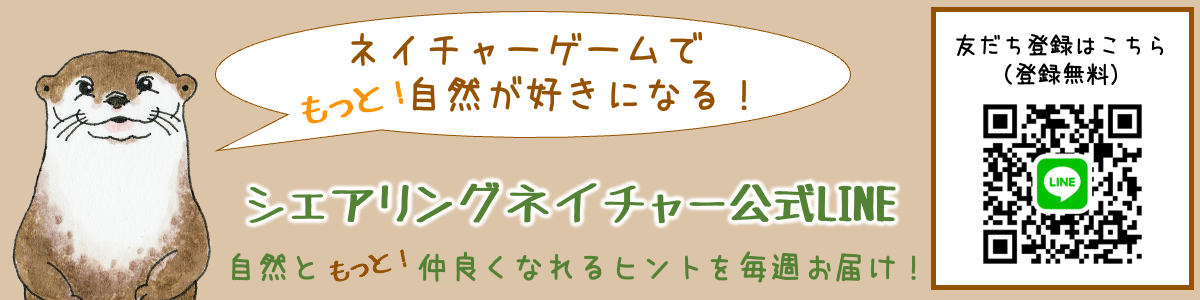この言葉を知っている人は、多いのではないでしょうか。
これは、「神秘さや不思議さに目を見はる感性」(『センス・オブ・ワンダー』p23)を意味し、
アメリカの作家で『沈黙の春』を著して環境保護運動のきっかけを作ったレイチェル・カーソンの代表作として広く知られています。
彼女の著作を翻訳し、その思想や自然への愛情を多くの人に伝え続けてきたのが上遠恵子さん。
94年目の春を迎えた上遠さんの目に今映るものや
〝自然〟と〝子ども〟に向き合う大人たちに伝えたいことを伺いました。
レイチェル・カーソン協会会長
東京薬科大学卒業後、東京大学農学部農芸化学科研究室勤務、学会誌編集者を経て、1988年にレイチェル・カーソン日本協会を設立。レイチェル・カーソンの研究をライフワークとし、『海辺生命のふるさと』『潮風の下で』『センス・オブ・ワンダー』などレイチェル・カーソンの著書の翻訳を多数手がける。

待ち合わせた喫茶店で、穏やかにほほ笑んで迎えてくれた上遠さん。お店がある田園調布に、幼少期からずっとお住まいだそうです。
もう少し暑くなる頃には、田園調布でもね、フクロウが鳴いていたんですよ。夏の夜に、母がね『ホロ助、呼んでみようか』って言うの。両手を組んで息を吹き込み、ホーホーってすごく上手にやってくれたものです。明かりを全部消して、息をひそめて、縁側にしゃがみ込んで待っていると、庭の木にやってくるんですよ、本当に。
〝バサッ〟なんて音がすると、幼かった私は、もう、ものすごくドキドキしてね。おそらくそれはアオバズクで、あまり大きくはないのだけど、そのときは絵本に描いてあるような、大きなフクロウがいると思って、もう、とにかくすごい高揚感でね、今でも思い出しますね
そう、少女のように目を輝かせ、原風景を語る上遠さん。『センス・オブ・ワンダー』に出会う前から、その感性は育まれ、今もみずみずしくあせないままです。胸にはフクロウのブローチ──ずっと愛着があるのかもしれません。ページをめくるたびに、目の前に豊かな自然の情景が浮かぶ『センス・オブ・ワンダー』。レイチェル・カーソンの言葉が心地よくそして温かく響いてくるのは、レイチェル・カーソンと同様、自然に触れ、親しんできた上遠さんの生い立ちから紡ぎ出された「日本語」があるからこそ。
私の世代は、英語教育はほとんどされていませんでした。だから、英語の本を訳して、なんて言われたって……七転八倒ですよ。
でも、カーソンさんの思いを伝えなきゃ、多くの人に読んでもらわなきゃ、ただひたすらその一心でしたね。そして、声に出して読んだときにも美しい日本語であるように、と思いながら訳してきました。あとになって、意訳が過ぎるのではないかと言われたこともありましたけれどね。
『センス・オブ・ワンダー』は読んでいて本当に〝そうよね、わかる、わかる〟と思うところが多かったのね。翻訳の作業は大変でしたけれど、カーソンさんと対話しているようでね、とても楽しかったです

子どもの頃の自然体験、そしてそこで出会う美しさや神秘さ、呼び起こされる感激、興奮、驚き、畏れは、その人の感性をかたちづくり、時を経てもよみがえる──。
上遠さんが〝伝えなきゃ〟と感じたレイチェル・カーソンの思いの一部です。翻訳本は、出版されてから30年以上たつ今も、多くの人に読み継がれています。
一方で、まだまだ伝えなければと感じる、今を生きる子どもたちの姿については……
けれど今、遊ぶといえばゲームばかりでしょ?二、三十年前、私の孫が小さかったときには、もうゲームが浸透していたけれど、飽きてくると外に出て遊んでいたんです。まだ、そういう時代でした。
今は次から次へと新しいゲームが作られて終わりがないですよね。おもしろいのかもしれないけれど、自分でああしてみよう、こうしてみようという実体験がない……。それは子どもにとって不幸なことだと思うんです。ゲーム漬けの子どもたちが大人になって子育てをするようになったら……そう思うと、とても心配です
いろいろなものが人工的になりすぎている、と上遠さんは続けます。
効率的であること、時間がかからないこと、生産性が高いこと、いつでもどこでも快適であること、手軽に興奮が得られること、これらを追い求め続ける社会は日常の景色をどんどん変えていっています。
子どもたちの感性を乏しくさせてしまうのでは、と上遠さんは警鐘を鳴らします。
そして、また別の危機感を上遠さんは感じています。
この辺りも、空襲でずいぶん焼けたんですよね。うちの近くの畑にシュル~って焼夷(しょうい)弾が落ちてきて、土に刺さってボーボー燃えてね。幸い、家は燃えませんでしたけれど、あんな恐ろしいことはありませんでした。
本当に、戦争が一番ひどい環境破壊。環境だけじゃなくて、人間の心まで傷つけてしまう。戦争から帰ってきた方が、戦争の話は一切しなかったという話を聞きますけれど、それは修羅場を見てしまって、口にできなかったんだと思うんですよね。
だから、もう絶対、平和じゃなきゃいけないと思いますね。8月15日、あの日の入道雲っていうのは忘れられないですね
命を軽んじるような世界であってはならない。それは、戦争を経験した私の遺言のようなものです、と上遠さん。
なにも自然いっぱいのところに出かけなくたっていい。道端に伸びたツクシや、タンポポの綿毛が飛んでいくのを見たり、サナギが羽化するのを見たりしてね。そうすると、自分以外の生命がこの地球上にたくさんいるということを知るんですよ。
小鳥や生きものを飼っていると、死んでしまうこともありますよね。〝もう戻らないんだ〟と、子どもはウェーン、ウェーンと泣く。そのとき感じた気持ちを大事にしてほしい。命に対する畏敬(いけい)の念を持たないまま大人になったら恐ろしいですよ
『センス・オブ・ワンダー』の中でレイチェル・カーソンは、子どもが自然に触れるとき、喜びや感動をわかちあう大人が必要であると述べています。上遠さんは、子どもとの向き合い方をこう語ります。
私は子どもたちと一緒に『これきれいだね』『サナギのときは土の中にいるんだよ』なんて話をしていたんです。そうしたらお母さんが来て『キャーッ、汚い!怖いからやめなさい』と言うわけです。
そんな、かわい子ぶって何を言ってるの?と思いましたよ。けれど、そう言うわけにもいきませんから、刺しもしないし、子どもはむやみに触らないから大丈夫ですよって言ったんですけどね。
虫が怖いとか、汚い、土はバッチイから触るな、なんて子どもに伝えてほしくない。土はいろんな生命を育んでいるのに……。『おもしろいね』『これ、よく見てみようか』って親が楽しめば、子どもは幸せな気持ちで触れ合えると思うんです。
子どもが自然に触れて、純粋に喜ぶ姿を通して、親もそういう感覚があったなと思い出すでしょ。親も変わらなきゃいけないと思うし、多くの親が変わっていくものです。そうあってほしいなと思います
子どもと自然体験をするときに、そばにいる大人の在りたい姿について上遠さんは続けます。
名前を教えるよりも『いいにおいね』『ふわふわしているね』と感覚を一緒に楽しむほうが、結局、子どもの記憶には残るんです。そして大人は子どもの興味や関心を共有して、今度調べてみよう、って誘うことがあってもいいんじゃないかしらね。大人は大変だけれども、本当は毛虫が怖くても、子どもと一緒に調べることもいい経験になりますよね
自然体験で培われたセンス・オブ・ワンダーは〝これ、なあに?〟〝もっと知りたい!〟の源です。たくさんの情報を簡単に手に入れられるようになったとしても、実際の手触りやにおい、耳を澄ませて聞こえた音、そのときに湧き起こった感動があってはじめて、知識に血が通い、意味を持つのでしょう。
上遠さんは、子どもたちに成果や結論を早く求めすぎないでほしい、と願っています。
いろいろな体験を積み重ねて身につくものであって、『そんなに急いじゃダメですよ』って言いました。子どもには子どもの時間がある。大人はそれを忘れてはいけませんね
子どもは一筋縄ではいきませんよね、と上遠さん。
ときに心にもないことを言うこともありますしね。
ずいぶん前の話になるけれど、遠足から帰ってきた見知らぬ子どもたちに、『どこに行ってたの?ドングリ拾ったの?』なんて声をかけたんです。そうしたら『ぼくたち、そんなネクラなことしないよ』って。
当時、ネクラという言葉がはやっていたんです。だからそんな生意気なこと言うんですけど、『ポケットにはドングリがいっぱい入ってるじゃない!』って言いたかったんですけどね。自然の中で『つまらない』なんて言っても、本心は楽しんでいたりする。大人は子どもの様子をじっくり見ることも大事なんじゃないかしらね。
そして、子どもたちに自分の感じたことをどんどん言わせてあげてほしいですね。近頃の子どもたちに『これ、なあに?』と話してもなかなか返事がない。間違えたら……、人と違ったら……と答えない。
突拍子もない方がイキイキするものでしょ?感じたことをしゃべらせて、いろんな感性があるんだということも、子どもたちに知ってほしいですよね
『センス・オブ・ワンダー』は毎年版を重ね、70版を数えます。
この本は、自分の心の在り様や、年齢によって共感する言葉が違うのもおもしろいなと思うんです。私が今、この歳になって、本当にそうだな、いいなと思う節があります。
――地球の美しさについて深く思いをめぐらせる人は、生命の終わりの瞬間まで、生き生きとした精神力をたもちつづけることができるでしょう。鳥の渡り、潮の満ち干、春を待つ固い蕾のなかには、それ自体の美しさと同時に、象徴的な美と神秘がかくされています。自然がくりかえすリフレイン――夜の次に朝がきて、冬が去れば春になるという確かさ――のなかには、かぎりなくわたしたちをいやしてくれるなにかがあるのです――(同書p)
来年のこの季節を迎えられるかどうか、わからない年齢ですからね。しみじみと感じています。 この頃はね、カーソンさんに『そのうち行くからわかるようにしてね』って言ってるんですけどね。もう天国にはいっぱい人がいるから、会うのが大変じゃない?まず両親やきょうだいに『やってきたよ』って話してから、カーソンさんに会いたいなと思ってるんです
うまくいくかわからないわね、と笑う上遠さんに、「カーソンさんは、日本中に『センス・オブ・ワンダー』を届けてくれてありがとうって、まず最初に会いにくるんじゃないですか?」と伝えると
とやさしく笑ってくれました。
でもね、必ず自然の中で感じた命のこと、思いやり、いろいろなことがまた戻ってくるんですよ。私はね、もう、そうだと信じることにしているの
〝信じる〟という上遠さんの、静かな、けれど力強い言葉に、なにか安堵感のようなものを感じました。同時に、託された思いの重さも感じました。いつもの公園で、森で、川で、春、夏、秋、冬と自然を感じれば、たくさんの命に満ちていること、そして人間はその一部であることがわかります。
センス・オブ・ワンダーがあふれれば、きっとやさしい世界になるはず。自分にできることはなんだろう……そう考えながら、空を見上げました。
※情報誌「シェアリングネイチャーライフ」Vol.42 特集(取材・文:茂木奈穂子 編集:藤田航平・豊国光菜子、校條真(風讃社))をウェブ用に再構成しました。
※冊子版の送付が可能です。「ネイチャーゲーム普及ツールの取り寄せ」をご覧いただき、お気軽にお知らせください。
(情報誌バックナンバーにつきましては在庫切れの場合がございます。ご了承ください。ウェブ版はこちらからダウンロード可能です。各号目次下部の<※PDFデータを開く>よりご覧ください。)