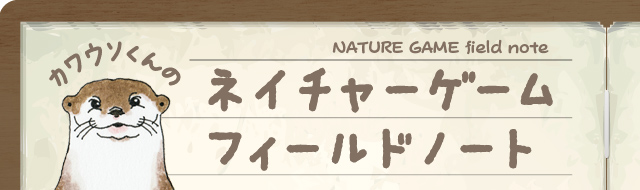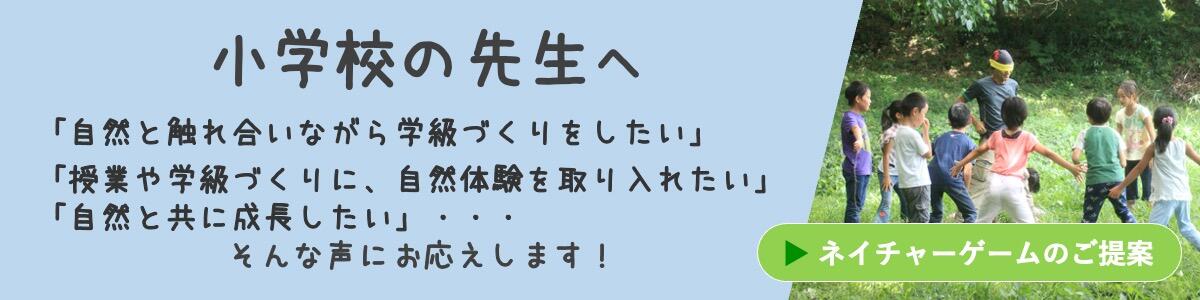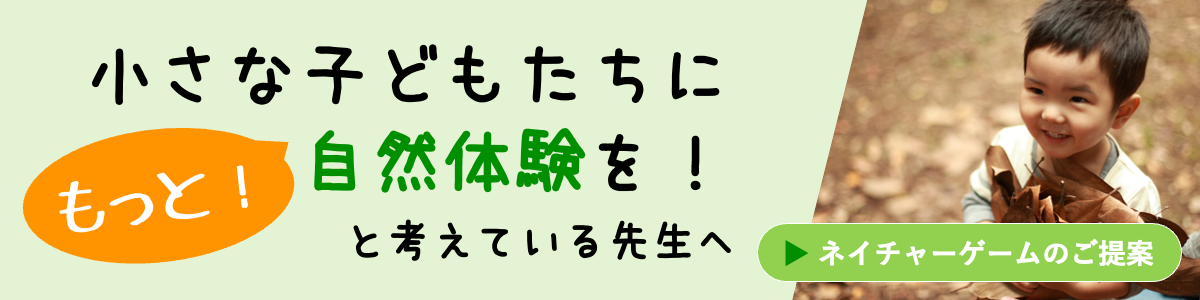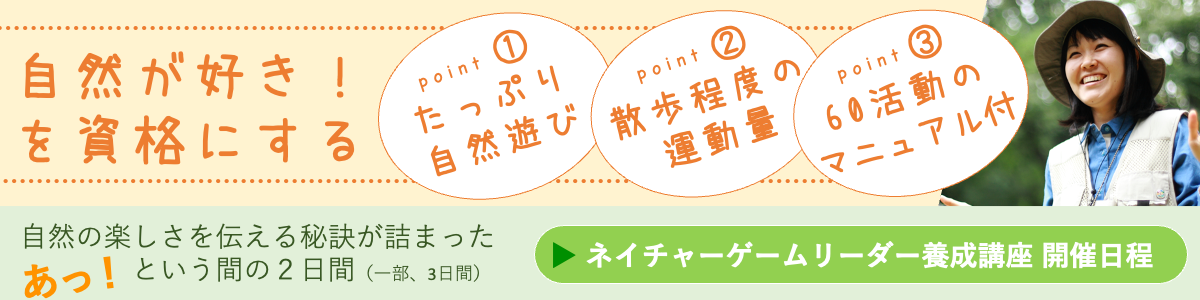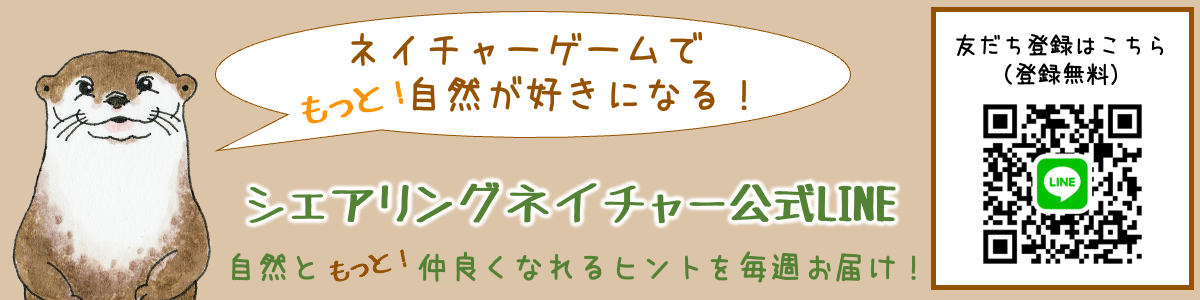環境教育関連の大きな動きとして、「環境教育等促進法」の基本的な方針の変更が挙げられます。
日本政府では、私たちを取り巻く社会的な状況や環境教育・ESD(持続可能な開発のための教育)の現状を踏まえて、5年を目途に基本的な方針を変更しており、2023年度に6回開催された環境教育等推進専門家会議及び意見募集(パブリックコメント)を経て、2024年5月に閣議決定しました。
今回の改定における主な変更点は下記のとおりです。
【主な変更点】
●環境教育の目的として、気候変動等の危機に対応するため、個人の意識や行動変容と組織や社会経済システムの変革を連動的に支え促すこと。
●環境教育において特に重視すべき方法として、これまで重視してきた体験活動に加えて、多様な主体同士の対話と協働を通じた学びやICTを活用した学びの実践を、学校、地域、企業等の様々な場で推進すること。
●学校内外での対話と協働による学びの推進に向けた、学校と地域・団体・企業等をつなぐ中間支援機能の充実による、学校の教職員の負担軽減と教育の質向上の両立を図ること。
●これらを推進する具体的な方策の一つとして、中間支援組織の強化等を掲げ、その足掛かりとしてESD活動支援センターや地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)及び地方環境パートナーシップオフィス(EPO)等の既存の中間支援組織の活用を図ること。
主な変更点の1つに、個人の意識や行動変容と組織や社会経済システムの変革を連動的に支え促すことが挙げられています。言葉で書くことは非常に簡単ですが、教育に携わる私たちにとっては長年の課題でもあります。
一方で、この課題に対してしっかりと向き合っていこうとする動きが最近活発になってきました。
私が所属する日本環境教育フォーラムにおいても、行動科学や認知心理学の専門家などの様々な知見から、環境教育のインパクトを高めるためのヒントを探るために機関紙「地球のこども」で特集を組みました。
今回、専門家の皆さまの記事を読んでいただくのが一番学びになると考え、紹介いたします。
(決して、楽をしている訳ではございません。私自身も特集を読み、これからの自然体験をベースとした環境教育に求められるポイントなどのヒントをたくさん得ることができました。)
【地球のこども2024年冬号】
特集テーマ:行動変容を伴う環境教育を目指して
●行動促進策の概論:但野紅美子さん(株式会社三菱総合研究所)
●研修転移を目指して!行動変化にこだわったアウトドア研修:小野彰太さん(国際自然環境アウトドア専門学校)
●学習科学をもとにした「未来を創る力」を育てる教育:白水始さん(一般社団法人教育環境デザイン研究所)
●行動変容ステージモデルなど行動科学の知見を取り入れた環境教育:三神彩子さん(東京ガス株式会社)
上記の特集記事については、公益社団法人日本環境教育フォーラムのウェブサイトより無料でご覧いただけます。
▶︎公益社団法人日本環境教育フォーラム ウェブサイト
環境教育はすぐに効果は見えず、じわじわと効いてくることから「漢方薬」みたいのものとして例えられます。
私自身は名古屋駅前の都会で幼少期を過ごしたため、豊かな自然体験を過ごしてきたとは決して言えません。
しかし、小学校時代の先生がネイチャーゲームのリーダーであり、都会においても「自然」と「子ども」をつなげるために様々なアクティビティを実践していたことを思い出します。
そして、それが私の環境教育の原点であり、現在の仕事にもつながっています。環境問題をはじめ正解がない課題/問いに取り組んでいくことが求められますが、ネイチャーゲームには、そのような時代を生き抜くための人づくりを進める力があると信じています。
●ネイチャーゲームをもっと知りたい方は
▶︎ネイチャーゲームリーダー養成講座を受講する
●ネイチャーゲームを体験したい方は
▶︎全国で開催しているイベントに参加する
●ネイチャーゲームの講師を呼びたい方は
▶︎講師依頼をして自分のイベントで実施する
公益社団法人日本環境教育フォーラム 事務局長
日本シェアリングネイチャー協会理事
大学卒業後に青年海外協力隊(職種:環境教育)として中東・ヨルダンへの派遣を経て、2014年より日本環境教育フォーラム(JEEF)に。入社後はバングラデシュやカンボジア、インドネシアでの海外事業に携わり、2019年11月より事務局長に就任。また、2024年からは環境省と文部科学省によって設置されたESD活動支援センターの副センター長を務める。 その他に、JICA環境教育OV会会長も兼務。